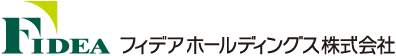サステナビリティ
サステナビリティ方針に基づく各種方針
人材育成方針
経営理念の実現に向け、従業員一人ひとりが行動指針〈Future7〉を主体的に実践し、地域やお客さまに寄り添い、それぞれが抱える課題の解決やニーズにお応えする、高次のコンサルティング力やソリューション提案力を身につけた人材を育成します。そのためには、一人ひとりのスキルに応じた各種研修(OFF-JT)、実践経験(OJT)、自己啓発(SD)を複合的に組み合わせ、従業員の自律的成長支援に不断に取り組んでまいります。また、多様な人材は新たな価値を生み出す源泉であると捉え、一人ひとりのモチベーション向上と自由な発想を促す個人の成長や経験の積上げ機会を設けていきます。
社内環境整備方針
従業員満足(ES)や自発的貢献意欲の向上を図り、これを起点としてお客さま満足(CS)の向上に繋げられるように、従業員一人ひとりが働きがいを持って能力を十分に発揮できる仕組みづくりと、安心して働き続けることができる働きやすい職場環境の整備に努めていきます。
また、性別や年齢などに関係なく様々な人材が活躍できる環境や仕組みを整備し、多様な人材が意欲をもって活躍する活力ある組織の構築を推進していきます。
人権方針
フィデアグループは、東北地方に根差し新しい価値を育む広域金融グループとして、地域社会の持続的な発展に貢献していきます。
地域社会の持続的な発展を目指すうえで、人権の尊重を重要な社会課題の1つとして認識し、本業を通じてこの解決に取り組んでいきます。
- 国際規範の尊重
世界人権宣言をはじめとする人権に関する国際規範を尊重します。 - あらゆる差別行為の根絶
性別、性的指向、性自認、宗教、信条、障害、人種、国籍等を理由とした差別や人権侵害を行いません。また、従業員一人ひとりの多様性を尊重し、あらゆるハラスメントや非人道的な扱いを根絶します。 - 人権に関する教育の実施
従業員一人ひとりが人権問題に関する正しい認識と理解を深めるため、研修をはじめとし、人権に関する教育を実施します。
投融資方針
- フィデアグループは、国連が採択したSDGs(持続可能な開発目標)の趣旨を踏まえ、グループ経営理念に基づく企業活動を通じた地域社会と地域経済の持続的な発展の実現に向け、地域における環境及び社会問題の解決につながる投融資を推進します。
- また、環境への負荷や人権問題など社会への影響の大きい事業等に対する投融資に関しては慎重に判断し、十分に留意します。
- 以下に例示するような事業に対して、積極的に支援を行います。
- ①地域社会や地域経済の持続的な発展に資する取組み及びその事業(創業及び事業承継を含む)
- ②気候変動リスクを低減する省エネルギーや再生可能エネルギー事業、脱炭素社会の実現に寄与する事業
- ③水資源や森林資源、生物多様性などの保全に資する事業
- ④少子高齢化に対応する教育、医療や福祉に資する事業
- ⑤農林水産業や観光産業をはじめとした地域産業の振興に資する事業
- ⑥防災や減災に資する取組み及びその事業
- ⑦その他、持続可能な地域づくりに資する事業
- 以下のような先には投融資を行いません。
- ①反社会的勢力及び事業
- ②人権侵害や強制労働への関与先
- ③非人道的な兵器の開発・製造の関与先や、規制・制裁対象先
- ④新設の石炭火力発電所向け投融資
ただし、例外的に取組みを検討する場合は、発電効率性能や環境への影響、地域社会への影響、個別案件毎の背景や特性等について総合的に勘案し、慎重に対応を検討
環境方針
フィデアグループは、気候変動をはじめとする環境への影響が経営リスクになることを認識し、脱炭素社会の実現を目指すとともに、「東北地方に根差した地域金融機関として地域社会と地域経済の活性化に貢献し、地域のお客さまとともに成長していく」というサステナビリティの考え方のもと、環境への負荷軽減とお客さまの環境に配慮した取組みを支援することにより、持続可能な地域社会の実現に貢献していきます。
- 環境関連諸法規の遵守
環境関連法令および規則等を遵守します。 - 金融商品・サービスを通じたお客さま支援
サステナブルファイナンスや脱炭素コンサルティングなどの金融商品・サービスなどを通じて、環境問題に取組むお客さまを支援します。 - 環境負荷の軽減
再生可能エネルギー等の活用により、事業活動における環境負荷の軽減に努めます。 - 気候変動への対応
気候変動は地域社会の持続性に大きな影響を与える重大な環境課題と認識し、脱炭素社会の実現を目指した取組みを行います。また、気候変動が地域社会に及ぼすリスクの軽減に努め、気候変動への対応に関する適切な情報開示に取組みます。 - 生物多様性の保全
生物多様性がもたらす恩恵を認識し、その保全に努めます。 - ガバナンス
気候変動への対応および生物多様性の保全に対する取組みの内容について、定期的にサステナビリティ推進会議で審議・報告を行うとともに、取締役会の任意の組織であるサステナビリティ委員会へ報告し、取組みの向上・改善に努めます。 - ステークホルダーとの対話
環境保全に対する役職員の意識の啓発に努めるとともに、地域社会をはじめとしたステークホルダーとの対話を通じ、環境保全活動の啓発と推進に努めます。